● こんにちは、まこちょです。
以前、助動詞will/wouldについての記事を書きましたが、助動詞という品詞は同じ意味なのにそれぞれ使い分けをしていたりして厄介なんですよね。
参考までにこちらの記事です
今回の助動詞も意外に使い分けが難しいshouldとought toについて解説します。この助動詞、「~すべきだ・~するはずだ」と暗記している英語学習者も多くいると思うのですが、なかなかどうして、一筋縄ではいかない助動詞なんですよ。
そこで今回も、will編と同様、根本にあるイメージを捉えながら学習していきましょう。ぜひモノにしていただいて今後の英語学習にお役立てください。
スポンサーリンク
目次(Contents)
これが義務を表す助動詞だ
突然ですが、例え話です。
とってもおもしろい映画を観てきたあなた。その感動を、まだそれを観ていない友人に伝えたい、観てもらいたい!どんな風に友人に勧めますか?
「いや、マジで絶対観た方がいいって!!」
そんなオススメの仕方ができますね。
では同じように、英語で伝えてみましょう。みなさんが連想する「~した方がいい」とはいったい何がありますか?「~した方がいい」は……そう、had betterがありますね、すぐに思い出した人も多いのではないでしょうか。そこで今回のセリフを英訳してみましょう。おそらくこのように表現するのではないでしょうか。
例
You had better watch it!
うん、なんか上手く表現できたように思えますが…本当にそれでいいのでしょうか。たしかに助動詞had betterは「~した方がいい」と義務を表す助動詞で有名なのですが、そもそも義務を表す助動詞は他にもまだまだあります。ざっと挙げるだけでも
must
have to
should=ought to
had better
と…思った以上にたくさんあるんですね。義務の助動詞表現は4つもあるんです。先ほど出てきたhad betterと、それからshould、must、have toと。
この中で最も相手への「オススメの度合」が強いのはどれでしょうか?といいますか、どの助動詞を今回は使えばいいのでしょうか。正解はmustだったりします。なぜ、こんなに義務の助動詞があるのにmustがベストと言えるんでしょうね?今回はここがポイントの1つだったりします。
もちろんそれぞれのニュアンスは大きく異なりますのでしっかりとそのニュアンスをつかむことが大事ですね。
スポンサーリンク
must ⇒主観(強)
mustには、「一つに絞る」というようなイメージがあります。悪く言うと、視野が狭くなっている状態なんですね。
そこからイメージを派生させて、「選択の余地がない」状態であり、かつ(「視野」というのは個々人の考え方という意味なので)「話し手の主観」が入り込んでいる、と解釈するわけです。
例
You must finish the work.
なんて言われた場合は、「つべこべ言わず、その仕事を終わらせてくれ!!」という気持ちが含まれているんですね。ちょうど、親御さんが小さい子に「いいからやりなさい!」と叱りつけているような感じでしょうか。
スポンサーリンク
had better ⇒脅迫
had betterには、「それをやらないと、後で困ることになるよ」という気持ちが裏に隠されているんです。特に「あとで困ることになる」という部分が重要で、これって【脅し】に聞こえませんか?そうこのhad betterは実はそうとう使いかたが限られるんです。
間違っても上司などに使ってはいけませんよ(笑)先ほどの例で言うと
You had better watch it!
は、観ておかないと困ることになるよ、という意味合いになってしまうんですね。その映画を観ることには、そんなに深刻な問題に発展してしまうのでしょうか……?そう考えると、ちょっと適切ではないように思えますね。状況的には、
You had better see your doctor.
「病院行った方がいいよ(後で悪化したら大変だから)」
の方が良さそうです。
mustもhad betterも、オススメの度合が強めというか、もはや「強制」「圧力」のような感じになってしまっているのがお分かりいただけましたでしょうか?そこから考えると、目上の方には使いづらい表現ですよね。
では、もう少し度合が弱いものを見ていきましょう。
have to ⇒客観
なんとhave toです。mustとの書き換えでよく出題される割には、その意味するところには違いがあるんですね。
have toを使った文の構造を、分解してみると、その意味の違いが見えてくると思います。例えば、
例
You have to study math.
という文について。この文の構造を、「状況を持っている(have)」→(どんな状況?)→「~するための(to 動詞の原形)」
と解釈してみましょう。そうすると、
「あなたは、数学を勉強するような状況を持っている(状況下に置かれている)」
という意味合いがあることが分かります。冷静に状況を分析しているような印象ですね。つまり、mustは主観的だったのに対し、「状況分析」つまりは客観的なのがこのhave toなんです。
ですので、You have to study math.と言われた場合、「客観的に状況を分析すると……最近数学の成績が下がってきているから、勉強するしかないね」と冷静に指摘されているというわけです。なかなか痛い所を刺してきますね(笑)。「あなたはそう思っていないかもしれないけれど、あなた以外の人は、あなたが勉強しなければならないと思っている」というニュアンスです。
mustとhave toについて詳しく知りたい方は以下の記事をどうぞ
should ⇒主観(弱)
さて、ここまで3つの表現を見てきました。それぞれ根本にあるイメージが大きく違うことはお分かりいただけましたでしょうか。ここまでの3つは、実は「選択の余地がない」「そうするしかない」という部分が共通しています。
最後は……もうお分かりですね、shouldです。「~すべきである」という日本語訳がメジャーですが、その日本語のイメージとは相反する結果ですね。
should(shall)には、「自然の成り行き」というイメージが隠れています。「空気を読む」ということですね。例えば
困っている人がいる!
↓
空気を読むなら助けるのが道徳的だよな
↓
Shall I help you?
というわけです。
そこから派生させて、相手へ勧めるときに使うshouldには「経験上そう思っているんだ」という意味合いがあると解釈します。その影には「俺はこうしたほうがいいと思っているんだけど」といった【あくまでの最終判断は本人にゆだねるけど】といった柔軟さがあるのがshouldの用法なんです。
ですから、冒頭でご紹介した「映画を観た方がいい」と言うときには、「俺が観た経験を踏まえると、とってもいい映画だったから観た方がいいと思うよ!」という意味合いになるので
You should watch it.
と言ってあげればいいんですね。
should = ought toか?
shouldはよく、ought toとの書き換えができると教えられます。「should=ought to」の書き換えを連想する英語学習者も多いのではないでしょうか。
ところが「must≒have to」であるように、こちらも性格には「=」と言えないのが難しいところです。実は、shouldとought toには、mustとhave toのときのような、「主観vs客観」という違いがあるんです。
ここで、shouldに含まれている意味合いをもう一度確認してみましょう。shouldは「自分の経験上、あなたに勧めたい」でしたね。
「自分の経験」というのが、相手へ勧める際の根拠になっています。自分の経験なんて、非常に主観的ですね。つまり、shouldを使ってのオススメは主観的という事になるわけです。
対してought toは、客観的な事実(法律、義務、規定など)が相手へのオススメの根拠にあります。これはもはや相手へのオススメというより、「必要不可欠であること、必然的で回避できないこと」について述べているんですね。
例
Parents ought to take care of and protect their children.
「親は子の世話や保護をするべきである」
民法の第820条では、監護及び教育の権利義務というものが規定されています。「親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う」というものです。
つまりought toは主観的なモノなどは目もくれず、法律上そう決まっているという観点で使うのです。「自分の経験」をもとに話をするようなshouldでは意味合いがずれてしまいますね。
このことを踏まえると、「義務」度合ランキング1位は、抗えない法律などを背負っているought toになるのかもしれませんね。
ただこのought to、特に否定文や疑問文は日常生活ではほとんど使われないようです。まあ専門家やコメンテーターなどではない限り、一般人が日常で法律などの話をする機会はそうそうありませんからね。
義務度合をまとめてみる
ということで、相手へのオススメ助動詞表現、度合ランキングをまとめてみると以下のような感じです。
①ought to …… 法律など、一般人が簡単に抗えないものが背後にある。
②must …… 話し手の主観、思い込みが強く、強制力が半端ない。
③had better …… 「後で困ることになる」という危機感、深刻な雰囲気が漂う。
④have to …… 冷静に状況を分析し、客観的に指摘している。
⑤should …… 話し手の経験を元に勧めている。ただし、聞き手に選択の余地はある。
あとがき

さて、今回はいかがでしたでしょうか。
学生時代に学習した日本語訳のイメージからは想像できない結果だったのではないでしょうか。「~すべきである」というshouldが最も度合が弱いのがいい例ですね。
また、should=ought toと書き換えを出題する割には、両者の間には天地の差があることが明白になりました。
このあたりを上手に使いこなして、自分の意見を押し付けるような強引なやつ、という誤解を与えないような英会話ライフを楽しめるといいですね。
また会いましょう。

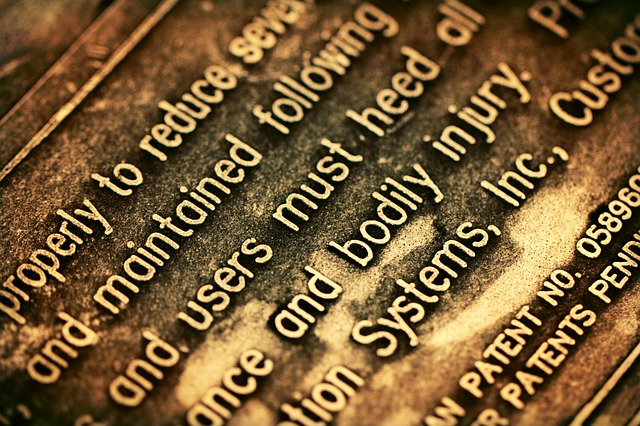





















コメントを残す